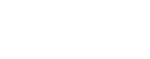【Geometry Nodes】Starノード【Blender】
星型を描くStar(スター)ノードを単体で解説。

| 使用ソフトウェア | バージョン | 備考 |
|---|---|---|
| Blender | 3.2 |
Starノード
日本語:スター
概要
星型を描くジオメトリノード。
ツノの数がパラメータで設定できるので、よくある星以外にもバリエーションが作れる。
出し方
Curve Primitive > Star
Points
ツノの数を設定する。
50のように大きくしてみても面白い形状になる。
Inner Radius(内径)
中央から凹部分の頂点までの長さ。
実際に測ってみると、上の長さがInner Radiusになるようだ。
Outer Radiusより大きくすると凹凸が反転するので注意。
Outer Radius(外径)
上とは逆で中央から凸部分の頂点までの長さ。
Twist(ツイスト)
Inner側の頂点を反時計周りに度数で回転する。
Outerは回転しない。
OuterとInnerのサイズを反転すればTwistで外側が回転するようにも出来るが...
わざわざそうしなくてもマイナスにTwistしてやれば形状自体は同じものが作れる(位置が若干変わるが)
頂点の位置が重要であれば場合によって使い分けると良いと思う。
Outer Pointsアウトプット
この項目は少し難しい項目。必要最小限の解説となっているので注意。
Selectionソケットの使い方が分かっていると楽。次の記事も参照してもらえればと思う。
Curve Primitive系の中で唯一このノードだけ2つ目の出力であるOuter Pointsを持っている。
先に結論を言えば凸側になっている点にTrueが付与されたデータが出ている。
確認
ctrl + shift + ノードをクリックでどんな値が出てるか確認できるViewerノードが出るので繋いで見ると
この状態でスプレッドシートを見てみるとどんな値が出力されているかがわかる。
結果は
赤枠で囲った部分に1と0が交互に現れている。
つまり外側の凸になっている頂点(Outer)にTrueが付与されている結果だ。
Outer Points使用例
例えば次のようなノードを組んだとする。
結果は
Starノードで作られた拡張点がCubeで置換された結果になる(カーブは消える)
ここでOuter PointsをSelectionに接続すると
内側のポイントが消えて外側だけが描画された(falseになっている点はInstance onn Points内にてポイントとして処理されなくなった)
つまりStarノードを使った時、次に繋がるノードで外側と内側の点を分けて処理したい場合に使えるはずだ。
SelectionインプットはBoolean(TrueかFalse)と明示されているがBooleanの代わりに数値でも良い仕様の模様。
v3.2では0より大きければ(0.001とかでも)Trueとして扱われることをテストで確認。
最後に
Selectionソケットに関しては別途記事を用意したので次を参照。